Miraiam編集長のりらです。連載企画「人生、。」は第4回目になりました。今回はなんと、めぶきが僕にインタビューをしてくれました...!!
めぶきです。りらさんとは高校2年生の秋に「Project:ZENKAI」で出会いました。
今まで、りらさんにはいつも私の悩みや不安を聞いてもらっていたので、インタビュアーとして、私がりらさんの人生や価値観を深掘るのは、少し不思議な感覚でした。
Miraiam編集長として、1人の若者として、自分との向き合い方、自分の人生を自分で作る方法について聞いてみました。様々な葛藤を抱える中高生の皆さんに寄り添った内容になっていると思います!
人生、。とは?
情報に溢れ、なんでもできてなにもできないこの時代を生きる私たちは、どんな人生を選ぶのだろう。
人生のことなんて、未来のことなんて、簡単にはわからない。
迷い、もがき、苦しみながらも、僕らはそれでもなお、人生を、生きている。
今を生きる若者のそのままの生き様を記録する新連載。
■僕が今見ている「生きることそのもの」の景色
めぶき:りらさん、本日はよろしくお願いします。早速ですが、まずりらさんがこれまでどんな人生を歩み、どんな景色を見てきたのかについて教えていただきたいです。
りら:小学校までは本当に普通の、帰るなりランドセル放り投げて公園に遊びにいくようなわんぱく小学生でした。ただ、中学生になってからは学校の集団授業や集団行動にひどく疲れてしまい、学校に行かなくなって。
その後、S高等学校(※)に進学し、そこで出会った恩師の影響で教育活動を始めました。それからは「Miraiam」を含め、志を同じくする仲間たちと様々な教育活動に取り組んできました。
※S高等学校は、N高等学校(学校法人角川ドワンゴ学園)の姉妹校である通信制高校。好きな時に、好きな場所で学習できることが特徴のネットの高校。(https://nnn.ed.jp/)
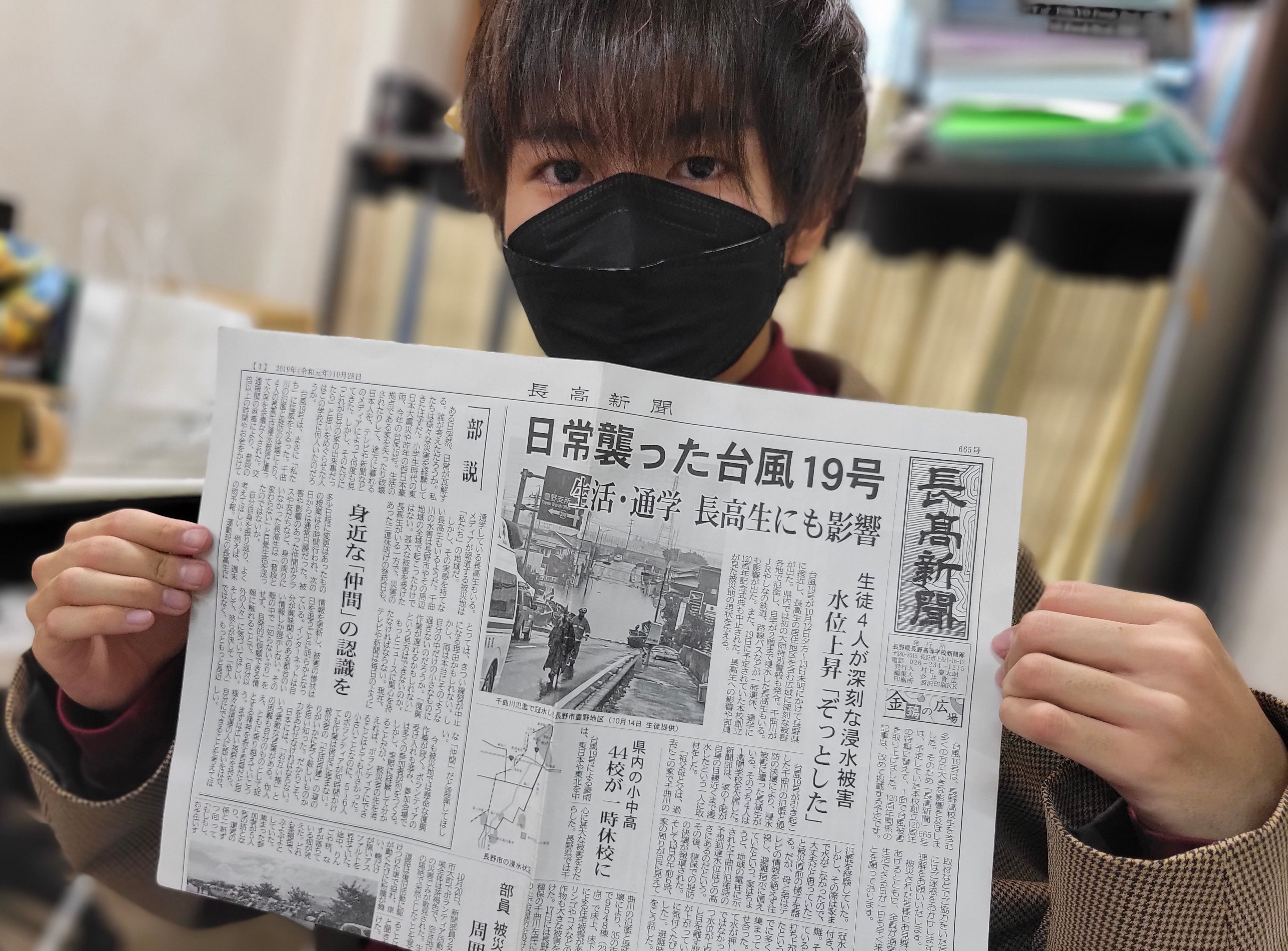
教育に関わる中で自分と向き合っていると、「生きることそのもの」に関わることに大きな関心があるなと気づき始めたんです。だから今、僕の目の前に広がっている景色は、「生きることそのものを作り出す」とはどういうことか、そのための媒体とは何だろうか、という問いになってくるのかなと。
めぶき:「生きることそのものに関わるものを作り出していきたい」とのことですが、それを実現することで、どんな世の中にしたいと考えていますか?
りら:僕の中での「人生を作る」というイメージは、「自分自身の手で、手触り感のある生を作れるようになること」なんです。
例えば、自分で食べ物を作れるようになるとか、自分自身で価値を生み出せるようになるとか。今は、労働の対価としてお金をもらい、そのお金で食べ物を買う。
という仕組みが当たり前だけれど、そういった経済や社会構造に頼りきるのではなく、自分自身の手で食べ物や住居、衣服といったものを作り出していける、つまり「生産者」になれることがすごく大事なんじゃないかなと。消費者でいるだけでなく、自分で作れる人を育てていきたい。そのための教育や媒体を考えています。個人としての目標は、地域の中に、そういう「手触り感のある人生体験」ができる場所を作っていくことです。
■「生産者」になるということ:エコビレッジとの出会い
めぶき:私は経済が発達した社会に生まれて、割と不自由なく暮らせてきたので、その構造にあまり疑問を抱いたことがありませんでした。りらさんがそこに危機感を抱いたきっかけは何かあったのでしょうか?
りら:僕も全然疑問を持っていなかったんですが、明確に意識し始めたのは**「エコビレッジ」との出会い**が大きいです。エコビレッジとは、自給自足の暮らしを村として営んでいる共同体。
去年、エコビレッジを訪ねる機会があり、そこで見た光景にすごく衝撃を受けました。明確なきっかけはその時です。その頃は、好きだった教育を仕事にし始めたのですが、教育だけで生きていくのは厳しいなと感じてもいました。そんな時期だったので、エコビレッジの生き方には衝撃を受けて。エコビレッジでは、自分たちの手で食べ物や住居を作っているだけでなく、お金からも自立していると感じました。誰かへの貢献が、必ずしもお金を介して行われていない。
ご近所さんと野菜をお裾分けし合ったり、みんなで助け合って生きている。その光景を見て、「世の中はお金だけじゃないんだな」と。お金に頼り切らない生き方を知ったことが、すごく大きかったですね。
■自分の人生の手綱を自分で握る
めぶき:りらさんのお話では「自分の手で作る人生」「手触り感のある人生」といった言葉が印象的ですが、なぜそれを大切にしているのでしょうか?
りら:端的に言うと、自分の人生は、全部自分で作っていきたいんです。以前、友人の母親に「りらは全部自分でやりたがるよね」と言われてハッとしたんですが、まさにその通りで、自分でやらないと気が済まない性分なんだと思います。
自分の人生を自分で作っていくことができるという実感、それは自己有用感に近いのかもしれませんが、人や社会といった自分以外のものに人生を委ねる感覚が苦手。僕の人生を生きる上で、「俺が俺の人生を生きる」ということが絶対条件としてあるのだと思います。
めぶき:自分を貫いて生きていると、周りから善意で「それで大丈夫なの?」と心配されることもあると思います。そういう時、どうやって自分を保ってきたのでしょうか?
りら:さまざまな方向から心配をいただくことは多々ありましたね(笑)。そういう意見を言われた時は、常に「それを実行して、本当に自分が幸せになるのか?」という問いに立ち戻るようにしています。周りのアドバイス通りにして不幸になったら、周りのせいにできるかもしれないけど、「周りのせいで不幸になった」と叫び続ける人生は嫌じゃないですか。そこは反骨精神でつっぱねています。
あとは、人に意見をされないために、多くを語りすぎないようにしています。自分が絶対に傷つけたくないもの、これだけは他人に何か言われたくないという「絶対値」を、簡単に人に明け渡さない。他人に自分を語る前に、まず自分と対話することが大事なのかなと思います。
■自分との対話と「違和感」を逃さないこと
めぶき:自分との対話をすごく大事にされているんですね。忙しい日々の中で、その時間をどうやって確保しているのでしょうか?
りら:意識して時間を取っているというより、生活の中に常に問いや対話がある感覚です。例えば、ご飯に誘われた時も本当に行きたいか自分に問います。
日々の対話の中で大事にしているのは、自分にとって良くなかった選択をちゃんと覚えておくこと。流されてしまった時に、自分がどう思ったか、自分の体がどう反応したか。その「違和感」を逃さないことで、自分が本当にしたい選択が研ぎ澄まされていく。良いものを選び続けるというよりは、良くなかったことの違和感の中から、自分を研ぎ澄ましていく感覚ですね。
めぶき:その意識は、いつ頃から持ち始めたのですか?
りら:高校1年生の期末試験くらいからです。高校入学からの1年、自分はゲームとテニス1筋の生活。それが悪いことだとは今は思ってないけれど、当時、試験が近づいてきたタイミングで「自分この1年勉強する時間たくさんあったのに、全然勉強できてへん」と大焦り(笑)。それが引き金になって、自分のためになることをしようと意識がシフトしていった感じです。
■新聞部での経験と「Miraiam」の始まり
めぶき:そこから新聞委員会に入られたんですね。
りら:そうですね。「学校の新聞委員会」という枠にとらわれず、本当に自由に、自分がやりたいと思ったことを何でもやらせてもらいました。YouTubeチャンネル立ち上げたり、トークイベントのゲストにクイズノックさんを呼んだり、筑波大学の教授に取材させてもらったり。
僕が通っていたS高は、生徒と一緒に学びの環境を作っていこうという先生方が本当にたくさんいる場所で、その影響はすごく大きいですね。自分の「やりたい」という気持ちに制限をかけず、「まずやってみようぜ」と背中を押してくれる。その感覚が、今の僕や「Miraiam」の活動の根っこにあると思います。
めぶき:「Miraiam」は、どういう経緯で始まったのですか?
りら:新聞委員会で活動していた頃から、教育の受け手である中高生だからこそ作れる教育があるんじゃないか、と考えていました。その思いをずっと持っていたところに、「会社を作って、N/S高を卒業した後も教育に関する活動ができる場所を作りたい」という仲間と出会って。彼と一念発起して出来上がったのが「Miraiam」です。
めぶき:りらさんが「教育」に関わる一番のやりがいは何ですか?
りら:自分だけでは体験し得なかった人生に携われることですね。教育者側として関わっていると、本当に色々な子と出会います。例えば「伝統産業の技術を継承する教育プラットフォームを作りたい」という子の夢を、一緒に作る立場として応援できる。人の人生を共に作れる感覚が、一番のやりがいです。
■中高生へメッセージ
めぶき:では最後に、これを読んでいる未来の自分や、過去の自分、あるいは誰かに届けたいメッセージはありますか?
りら:あなたが生きたいように生きてほしいし、そのための場所が「Miraiam」であったらいいなと思います。ご縁があれば嬉しいです。
めぶき:もう一つ、これは個人的なお願いですが、自分を貫きたいけど、まだ親の助けなしでは生きていけない…という葛藤を抱える中高生に向けて、アドバイスをいただけますか?
りら:まず大前提として、あなたの人生は、間違いなく親のための人生じゃない。これは認識しておいてほしいです。
その上で、いろんな人に会うべきだと思います。親以外に、頼れる人をたくさん作っていくことがすごく大事です。
僕も親の影響はありつつも、そこに依存しきらずに、自分で生きる道をたくさん作ろうと活動してきました。それはあなたもできる。本当に。僕も含めて、色々な頼れる人や生き方に出会っていく中で、親に縛られずに生きていく方法を自分自身で作っていこうとすることが、むちゃくちゃ大事だと思います。




